全国四大学合同リトリート感想記
2011年8月19日から20日にかけ、基礎医学研究者育成プロジェクト第一回リトリートが、東京ガーデンパレス及び本学医学部を会場に実施された。東京大学・京都大学・大阪大学・名古屋大学から教員と学生が参加し、オブザーバーとして山梨大学・群馬大学・横浜市立大学から学生が参加して、教員16名学生59名による盛大な催しとなった。東京大学はホスト校ということで、M1からM4まで23名もの学生が参加した。本リトリートは本学MD研究者育成プログラムの学生が主体となって企画運営し、目的を「基礎医学研究者を目指す同世代の学生が、研究活動の発表や意見交換を通じてお互いをよく知り、友好的なネットワークを構築すること」と定めて開催された。本リトリートの代表は東京大学M2の亀井亮佑が務め、亀井を中心に同大学M2の杉原圭、粟生智香、井上理美、川口智也、大塩博子、佐野俊春、M1の清田正紘で学生執行部を形成し、企画運営にあたった。
一日目はまず、前MD研究者育成プログラム室長・岡部繁男先生の開会の挨拶に始まり、各大学学生一名ずつによって、自身の実験と所属大学の医学研究者養成プログラムに関する口頭発表が行われた。本学からはPhD.-M.D.コースの安原崇哲(D1)が、「Rad54Bによるp53発現レベルの制御」という演題で口頭発表を行った。発表後の質疑応答は大いに盛り上がり、多くの学生参加者にとって良い刺激となったようであった。研究内容に加えて、各大学の特色ある医学研究者養成プログラムの情報を聞けたことは、自分の大学のプログラムの長所短所を見直すきっかけにもなり、非常に有意義であった。
次に、学生によるポスターセッションが行われた。お互いをよく知るという本リトリートの理念に則り、ポスターセッションでは参加学生全員に発表を義務付けた。そのため、全ての参加学生と考えや研究テーマを共有しあう良い機会となり、夜遅くまで活発な議論が続いた。多様な分野の視点に触れると同時に、自身の実験系や研究の方向性を見つめ直す大変貴重な場となり、交流も深まったと思われる。
二日目は、会場を東京大学医学部に移してキャリアセミナーが行われた。キャリアセミナーには、横浜市立大学医学部循環制御医学から横山詩子先生を、ヘルシンキ大学Molecular/Cancer Biology LaboratoryからTuomas Tammela先生をお呼びし、MDを持って研究をする意義やご成功のきっかけなどについてお話を伺った。横山先生には、女性が育児をしながらも研究を続けていくために何が必要かや、臨床から基礎研究に移られたきっかけなどをお話しいただいた。一方Tammela先生には、ヨーロッパの医学教育制度・研究制度の特徴や、基礎研究者として生きていくために必要な資質などをお話しいただいた。
その後、MD研究者育成プログラム室長・吉川雅英先生の閉会の挨拶を経て、東京大学医学部のラボツアーが実施された。ラボツアーでは学生が小グループに分かれて本学大学院医学系研究科の研究室を二つずつ回り、教授の先生方と研究テーマに関して熱いディスカッションを行った。
本リトリートは、同世代の学生同士が共に将来のキャリアを考える、貴重な二日間となった。また、お互いの研究内容を知ることで、研究へのモチベーション向上につながったのは間違いないであろう。

(第一回全国四大学夏のリトリート代表 亀井亮佑)


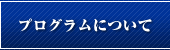
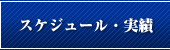
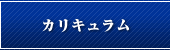
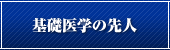
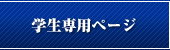

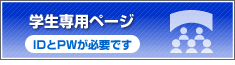
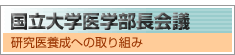
 HOME
HOME