FAQ
| Q | 研究には興味があるのですが、自分に素質があるか分からず、一生の仕事として選択するには迷いがあります。 |
| A | 若い方にとって当然の疑問だと思います。このプログラムの最大のメリットは、一流の基礎研究室で研究の現場を体験することで、自身の研究者としての適性を通常の修業年限(6年)の間に確認できることでしょう。時間を有効に利用して、自分自身のキャリアパスを真剣に検討する機会であり、これにより卒業時の進路選択を確実に行える一助となります。 |
 |
基礎の研究室に行かなくても、卒業後に臨床科に所属しながらでも研究はできると聞きました。研究者にはなりたいのですが、わざわざこのプログラムに入る必要があるのでしょうか。 |
 |
プログラムの特徴は大きく分けて3点あると考えています。一つ目は、定期的な少人数ゼミに参加することで、プレゼンテーションやディスカッション・スキルといった研究コミュニケーション能力を磨く機会が豊富にあることです。ここにはMedical Research Communicationsも含まれており、このような教育が体系的に行われるのは、医学部では今のところこのカリキュラムだけです。 二点目は若くて可塑性が高いうちに研究の方法論を学ぶことで自身の研究能力を飛躍的に向上させる契機となることです。研究とは未知への挑戦であり、斬新で革新的なアイデアが求められているため、若くて柔軟性が高い時に科学的思考のトレーニングを開始することが非常に重要です。そのため、このプログラムでは学部段階から積極的に基礎研究室で実験を行い、研究活動を専門として取り組んでいる人々から早期に研究教育を受けることを推進しています。このプログラムを履修することで得られる研究的経験は、将来臨床教室で研究する場合でも、必ずプラスになると思います。臨床科に所属している若手研究者にとってしばしば問題となるのは、自分が興味を持っている研究対象があってもそれを具体化するための方法論を学ぶ指導者を見つけることが出来ず、ある程度の研究結果が出てもその解釈や次の段階への発展の道筋を独力で見つけるための教育を受けていない、という点です。本プログラムに参加することで、基礎医学系の研究室での「本格的な研究ストラテジー」を身につけることが出来れば、将来臨床科に所属する研究者にとっても非常に大きな武器になると思います。 三点目は、研究を志す仲間とのネットワーク形成やサポートが得られることです。プログラムで企画される種々のゼミや交流会を通じて、同級生はもとより、上級・下級生や他研究室のスタッフ、さらに他大学の、「同志」ともいえる研究仲間と人脈を構築することができます。研究は最終的には極めて個人的な知的作業ではありますが、研究が高度化・複雑化した現在、一人で完結する研究は稀となっており、お互いを補完しあうようなコラボレーションがますます重要となってきています。プログラム参加で培われたネットワークは将来の研究に必ず活きてくるでしょう。また長い研究者人生が右肩上がりの一本調子で経過するということは実際には少なく、そのような時にキャリアについて参考にできる先輩や精神的な支えになる仲間とのつながりは大きな助けになりえます。また折々にプログラム室スタッフに相談でき、必要なサポートが得られることも大きな利点と思います。 |
 |
経済的な面が心配です。学費は通常の授業料以外にいくらかかるのでしょうか、また海外留学や遠隔地での学会参加の費用は自分で負担するのでしょうか。 |
 |
まず授業料は同額で差額はありません。また、学会参加の費用は、基本的には所属研究室の研究費から支出されるなどの方法で、学生の余分な負担は最小限にする予定です。海外留学の場合は、奨学金などの経済的援助が必要になりますので、どのような可能性があるかについては所属研究室と育成プログラム室が協力してそれぞれの学生さんにとっての最善の方法を見つけます。 |
 |
臨床の授業や実習を受けて、そちらにより興味を持った場合、一般コースに変更することは可能でしょうか。また、逆に、授業と並行してではなく、研究に全ての時間を使いたくなった場合、PhD/MDコースへの変更は可能でしょうか。 |
 |
このような場合、まずはプログラム室教員に相談いただきたいと思います。あまりに頻繁にいくつかのコースを行き来すると、カリキュラムの整合性がなくなってしまいます。プログラムの変更についてはよく事情を伺って相談した上で決定したいと思います。ただ、基本的にMD研究者育成コースでは、一般コースの内容は全て履修していただく仕組みですので、もちろん一般コースに変更することも、PhD/MDコースに変更することも、制度的には可能です。 |
 |
M2の時期には試験の連続になると聞きました。それとこのコースは両立できるでしょうか。 |
 |
授業を受けるばかりの日々が続くと、学んでいる意義が自分の中で薄れてきて勉強するモチベーションが下がることがよくあります。一方、このコースを履修すると、研究に関連する内容やディスカッションで聞いた内容について「なぜ?実際は?」というより深い疑問がわくようになり、かえって授業も研究も効率的かつ意欲的に取り組める、という可能性は高いのではないでしょうか。両立は時間的には大変でも、物事の真理を探りたい性向の人には精神的に得るところは多いと思います。 |
 |
当コースでは週あたり何時間程度研究に費やすことを想定しているのですか。 |
 |
これは所属先の研究室や指導してくれる人によっても異なると思います。また、研究というのは同じ時間をかけたからといって同じ結果が出るわけではないので、残念ながら一概には言えません。本来、学生の間は課外活動やアルバイトを通じて人生経験を積むよい機会でもありますので、可能な限り並行してやっていただければ、とは考えていますが、履修した場合は当プログラムに関係することを第一優先でお願いします。 |
 |
カリキュラムを作る段階でも参加したいと思いますがどうでしょうか。 |
 |
当プログラムは、研究者として必要な自主性をはぐくむために、参加学生の自主性を尊重した運営を行っています。履修する方々は与えられるものを待つのではなく、自ら積極的に意見を出し行動して、自分にとって有意義なものを作り上げていく努力が不可欠です。それを通じて、このプログラムを一緒に育て、自分が所属することを誇りにできるようにしていきましょう。 |
 |
下級生に教えるなんて、大丈夫でしょうか。 |
 |
「人に教えること」は、実は最上の学習方法です。教えてみて初めて、自分のわかっていないことが明確になっていくものです。必要なときにはどんどん教員のサポートを頼みながら、各種のゼミや発表会では、自分の出来ることからでよいので、積極的に下級生をリードしコーディネート・マネジメント能力を磨いてください。 |
 |
国家試験合格後、博士課程進学前に臨床研修を行うことは可能でしょうか。 |
 |
当コースでは、原則として大学院に進学していただくこととしています。指導する側としては、生半可な気持ちで参加して欲しくないからです。できれば学生のうちに、大学内外で臨床の現場をよく見て欲しいと思います。しかし、よく相談した上で、熱心に履修したが研究に適性を感じなかった、などの事情があれば、卒後すぐ臨床研修に進む可能性は、否定しません。 |


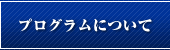
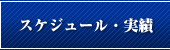
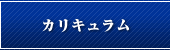
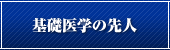
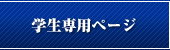

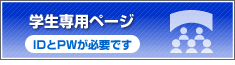
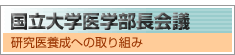
 HOME
HOME